恐れていたことが起きたと言えようか、それとも喜ばしいことが起きたと言えるか?
今回の事案は前者であろう。
ワールド・ベースボール・クラシックが日本国内においてはNETFLIX限定配信となることが明らかになった。
日本のメディアにとっては寝耳に水だったろう。まさか日本で大人気の競技の国際大会の放映権が海外の、それもストリーミングサービスに取られるとは思わなかった人も多いはずだ。
確かに、近年こうした国際大会はテレビで見られないことも増えているのも事実だ。近年でもサッカーワールドカップアジア予選の放映権はDAZNが獲得しており、それ以外にも様々な競技が地上波中継から消えてきた。
ここは、今回の出来事を冷静に見てみたいと考える。
利点
私のような、すでにNetflixに登録している野球ファンにとっては良い面が多い。
利便性
すでに登録しているという前提はあるが、追加の負担なしにいつでもどこでもWBCの全試合が見れるというのは良い点だ。
例え、手元にテレビが無くとも、外出中であろうと、スマートフォンなどインターネットに接続できる機器があれば、いつでも試合が見られる。前回大会も配信があったが、やはり手軽な視聴ができたのは良かった。また、録画できなくともいつでもアーカイブ視聴できるのは利点だ。
加えて、これまでは全試合を見るためにはケーブルテレビと契約して、再放送などの放送時間を待つか録画するというのが基本だったが、試合が開始さえすればいつでも視聴できるというのは、海外勢同士の試合も観戦したいようなファンにとってはうれしい話だ。
Netflixのコンテンツ力
また、Netflixは上質なドキュメンタリーを数多く作っていることも特筆すべき点だ。
Netflixが制作している、自動車レース最高峰のF1グランプリを追ったドキュメンタリーである、「Formula 1: 栄光のグランプリ」(原題:Drive to Survive)はアメリカ大陸を中心に高い人気となり、F1不毛の地とも言われたアメリカでF1が大人気となった。
今回もこうしたドキュメンタリーなどのコンテンツを通じて、日米のプロ野球以外にも、イタリアやイギリス、ブラジルなどの野球後進国に注目が集まる可能性もある。公式からもこうしたコンテンツを配信するという声明も出ているため、独自コンテンツを制作する可能性は高い。
放映権への注目
加えて、放映権ビジネスに注目が集まることも重要である。
こういった放映権ビジネスについて、日本野球界はMLBと比べて1〜2周遅れといえる状態である。実際問題、プロ野球においては放映権が統一されておらず、チーム間で資金差が生じている。
その上、放映権料が最大化されていないために、リーグ全体としての資金力もMLBと比べて弱い。実際問題、MLBはNPBの10倍の放映権料を得ているため、MLBが圧倒的資金力で日本の野球界を刈り取り場にするということも多い。
さらに、プロ野球ファン(主にセ・リーグファン)にとっても、放映権が統一されていないために多くのプラットフォームと契約せねばならず、頭痛の種となっていた。今回の放映権の獲得でこういった放映権問題はNPB主導のもとで解決に向かうのではないかと私は推測する。
問題点
しかし、今回のはあまりにも性急な話だ。先述のようにノーモーションでこの発表だったため、衝撃はプロ野球ファン全体に襲った。
ライト層の問題
野球ファンが地上波放送が無くなったことで危惧する声の多くが、野球に日常的に触れない層が見ずに、野球を知っているが、日常的に野球を見ない「ライト層」の野球人気がWBCを通じて獲得できないのではと危惧している人が多い印象だった。
これほどの大大会が地上波で突然全く見れなくなるというのはおかしいと言える。オリンピック、サッカー、ラグビーなどの多くの世界大会は地上波テレビで視聴可能だ。
DAZNが独占配信権を獲得した日本代表戦のワールドカップアジア予選ですら、ホームゲームは地上波放送で見れた。そのような中で何も見れないというのは大きな懸念だ。
日本のメディアはインターネットが強くなったと言われているが、前回大会での地上波放送は視聴率40%を獲得している。それは日本のライト層に向けて大きな宣伝となり、プロ野球の観客動員数拡大が生まれたのではないかと私は考える。ライト層がなかなか見ないのは難点だ。また、多くの場所で同時視聴がなされており、テレビが置かれている公共施設や店舗では、即席パブリックビューイングが行われた場所も多い。
ちなみに、Netflixはパブリックビューイングを規約で禁止している。村上宗隆のサヨナラ打や優勝の瞬間の反応集は同時視聴の良さを痛感したが、今回は叶わないかもしれない。
無料で見れていたコンテンツをお金を払ってみる人がどれだけいるかも問題だ。
WBCなど、野球の国際大会やビックマッチはどのような媒体であれ、無料で視聴できた。
そのような中で、野球を課金して視聴する人はそう多くないのではと危惧する。我々のような野球好きはWBCの視聴のために2000円くらい払えるという人も多いし、実際に実行している人も多い。しかし、ライト層はどうか。野球のために1000円を払えるか?という質問についてNOという人も多いはずだ。すでにNetflixに契約している人は1000万人以上とされているが、テレビが視聴できる世帯の1割以下だ。視聴者数はグッと減りそうだ。
リーチ力
例え、無料配信したとしても、今度はリーチ力に問題がある。
例えば、テレビであれば、電源を入れて何回か選局すれば野球中継に辿り着ける。
しかし、Netflixなどのインターネットメディアだと、まずそのサイトにアクセスせねばならないことが問題だ。さらに、検索→選択→視聴という工程を踏まなければならない。
我々のようなヘビー層やどうしても大谷らの勇姿がみたい人々にとってはまだ良いが、何となく見てみようという層に対しては、膨大過ぎるコンテンツの前に辿り着かない可能性すらある。
もちろん、トップページに表示されるとその工程が圧縮されるためにまだいいが、アルゴリズムが邪魔をしてスポーツに興味がないと判定されてしまえば、たとえその人が潜在意識で野球(WBC)にほんの少し興味があったとしても、WBCに届かない。
その他の問題
そもそも、Netflixがどれほどの熱量でWBCを宣伝するかも問題だ。地上波テレビや新聞などのマスメディアで多くの広告を出稿し、人々の目に触れるのであればまだいいが、さほど宣伝に注力せずに、各種メディアが黙殺状態になれば、宣伝が足りずに、2006年当初の野球ファン以外知らない大会というレッテルを貼られる可能性もある。
しかも、その金は日本に流れることなく、アメリカで回ってしまうのが日本の野球ファンにとって看過できない問題である。
前回までの放映権交渉の窓口は読売新聞であり、日本企業が日本企業を相手に放映権を売却していた。しかし、今回はMLB傘下のWorld Baseball Classic Incが直接交渉し、プールの主催者が知らぬ間にアメリカの会社と契約しているという事態となった。(なお、NPBは知らされていたと明かしている。)
もともと、利益のほとんどはMLBに入り、日本には数パーセントしか分配されないといういびつな構造が当初からあった。2006年もこの構造を理由に出場しない可能性もあった。そうした中で、プールステージは数少ない、日本野球界の経済が回るチャンスだった。
しかし、今回の出来事で、WBCで日本は蚊帳の外であることをまたしても痛感された。
原因
メディアの競争力低下
そもそもの問題点として、日本のメディアは金や競争力が無いことが今回再び明るみになったのではないかと考える。やはり、近年のテレビの失速は目に余るものがある。
前回のワールドカップも、NHKと各民放が結成しているジャパンコンソーシアムが放映権料が払えず、日テレ・TBS・テレ東が中継から降り、残りのNHK、テレ朝、フジも予算が足りない状況で、中継が消滅するのではないかという心配を救ったのは配信で成長中のABEMAだった。これは、テレビの終わりの始まりではないかという声も存在した。
今回の放映権交渉に至ってはMLB側がそもそも地上波をあてにしていないという報道もあった。
これは憶測による批判になるが、各放送局がケーブルテレビやCSなどの衛星放送などに力を入れなかったことや、一部事務所がインターネット配信を規制してテレビ番組を配信させなかったのはテレビ局の稼ぎ方を制限したと言えてしまう。テレビ局が広告収入以外の稼ぎ方を不動産以外で知らなかったのではと思う。
テレビ局が自社発のオンデマンドサービスに注力して、覇権を取っていた、ないし海外配信サイトと戦えるくらいの力があったり、ほかの稼ぎ方を見つけていた場合、こんなことにはならなかったかもしれない。
とはいえ、この状況が外圧抜きに変わることは無かっただろう。近年のプロスポーツの稼ぎ方において、放映権は欠かせないものだったにもかかわらずだ。
放映権料の問題
だが、日本が放映権料を吹っ掛けられすぎているのも事実だ。
2018年のFIFAワールドカップでは、日本は600億円を支払ったが、これはアメリカに次ぐ2位であり、国際連合の分担金の形相を示している。
また、日本はスポーツ大国とされており、経済状況からメディアも金があると思われている節があるが、間違いであろう。メディアは疲弊し、スポーツ界も常に資金不足だ。
アマチュアリズムが根強いためかどうかは知らないが、金はあなたたちが思っているよりかは日本スポーツ業界に回っていないと、海外スポーツ団体には言いたい。
そもそも、WBCは日本代表戦しか地上波中継されないというのも遠因だ。オリンピックやワールドカップのように日本代表戦以外が中継されてこなかったのは問題だった。
前回のWBCの放映権料は20~30億円とも言われているが、地上波中継や無料配信したのは7試合だった。ちなみにだが、FIFAワールドカップは地上波全体で150億円で41試合を地上波中継した。一試合当たりのコストパフォーマンスでは、WBC4億、W杯3.6億と、ワールドカップの方が良かった。また、海外サッカーというコンテンツを午前中や深夜という枠で中継できるのはあまりにも有効だった中、WBC中継には二の足を踏むことも理解できる。
地上波放送の行方
とはいえ、Netflix側が地上波を頼った結果、地上波放映が実現する可能性はある。
サブライセンス
近年、コストシェアの観点から、無料放送局と有料プラットフォームが放映権料を共同購入することが多く、ヨーロッパでは、地上波放送団体である欧州放送連合と有料放送局や配信プラットフォームを展開している米・ワーナー社が、共同で2026年から32年に行われるオリンピックの放映権を購入したことが放送業界で話題となった。
もしも、Netflix側が放映権料の回収が単独では厳しい情勢であると考えた場合は、費用を肩代わりしてもらう代わりに放映権のサブライセンス(放映権の再付与)をテレビ局に与える可能性もある。
また、CMなどの広告が入らないのであれば、WBCから日本のスポンサーが引き上げる可能性もあり、スポンサー料を補填するか、放映権を割譲するかの二択をMLBに突き付けられた結果、地上波放送へのサブライセンスの付与を渋々受け入れるなんてこともあり得る。
技術協力
それに加え、Netflixにはアナウンサーや中継のノウハウがないこともテレビ局にとっては交渉材料になりうる。
もっとも、これまでの衛星放送ではすべての試合で日本語での中継をしてきたと考えると、現地制作の映像を何もせずに垂れ流しというわけにはいかないはずだ。そうでないと野球ファンのヘビー層から大ブーイングを受けかねない。
実況もフリーアナウンサーだけでは成り立たない。さらに、オープン戦や他競技も行われるため、稼働可能な質のいいフリーアナウンサーはいないなんてこともあり得る。
一方で、地上波では日常的に野球中継を行っているスポーツ専任のアナウンサーが多く、他スポーツ中継も最近では少ないために稼働できる可能性は高い。
もしかしたらアナウンサー派遣という条件で地上波中継も可能性がある。TBSの南波雅俊アナウンサーがWBCで実況する夢を再び叶えるのか、ラヴィットでB’zを熱唱するかはここにかかっているかもしれない。
読売新聞の動向
ほとんどありえない話ではあるが、東京ラウンド主催の読売新聞がパワーを使って、NPBの選手やドームそのものを貸さないなどの強権発動というウルトラCもある。
そうすれば、日本大会は社会人中心となるため、日本代表はセミメンバーとなる。そうすると、前回フルメンバーで優勝したこともあって、たとえ負けても、NPBがフルメンバーで挑むプレミア12で勝ったほうが偉いと言い放つことも不可能ではない。
しかし、会社の指示などの選手起因の理由以外で撤退が決まるのは良くない。国とチームと違いはあれど、選手の意に反して撤退を決意したモスクワオリンピックの二の舞になってしまう。そうなれば、選手とオーナー陣の対立になる可能性もあり、2004年の再編問題以来の惨劇を演じかねない。
まとめ
今回の放送について、まだまだ不透明なことは多い。もしかしたら、Netflixがサブライセンスを販売するかもしれないし、本当に独占放送するかもしれない。
だが、時流は待ってくれないのかもしれない。現実問題、放映権料は上昇の一途を辿っている。
有料配信プラットフォームの台頭やPPVの普及以降、ボクシングや格闘技が無料放送から消えて久しい。先述するF1グランプリが無料で見れた時代は過ぎ去り、日本を含む各国で有料放送が基本となっている。他にも様々なスポーツが有料放送となっており、アメリカでも、もともとWBCは無料で見ることができず(2006年は有料スポーツ専門局のESPNが中継。)、アメリカのスポーツ好きは多くのプラットフォームと契約しているのが常だ。
今回の問題は、単に先延ばしにしていた問題がついに来ただけとも言えよう。
この大型の放映権契約により、日本代表が莫大な賞金を得られる可能性もわずかながらある。MLBの資金確保のために始まった大会ではあるが、これで出場した代表選手が、一年分の給与に当たるレベルの莫大な賞金を得られるなら仕方ないと言える。
しかし、これだけは分かった。テレビの力はまだまだ偉大である。そう感じた人はあまりにも多いはずだ。テレビ離れだのオールドメディアだの色々言われているが、まだまだ「娯楽の王様」は死んでいない。前回のWBCで、そして今回の放映権で野球ファンは痛感した。
また、今回の事で、社会的に重要なスポーツイベントは誰もが無料で視聴できるべきという考え方である「ユニバーサル・アクセス権」についての法整備が叫ばれる可能性もある。
現にサッカーではすでに同権を法整備をJFAが求めており、野球・サッカーの二大スポーツが求めたら、政府も動くかもしれない。
果たして、今回のWBCはどのような媒体で見ることになるだろうか?期待と不安が入り混じる中、2026年3月のプレーボールを待ちたい。
最後に
この放映権戦争における、ここまでの最大の敗者がこれまで静かに全試合をケーブルテレビで中継し続けたJSPORTSであることは記しておきたい。
恐らく、他社が有料での独占放映権を獲得したとなればJSPORTSは放映権を得られない一番の対象だろう。地上波放送の力こそ終わっていなかったが、衛星・ケーブル放送は本当に終わりつつあると私は近年痛感している。
特にスポーツ中継はインターネット配信に取られつつあった。そして今回のWBCの放映権。もう、衛星放送に体力は残っていないかもしれない。
JSPORTSの今までの中継に感謝をこめて……
参考資料
(順不同)


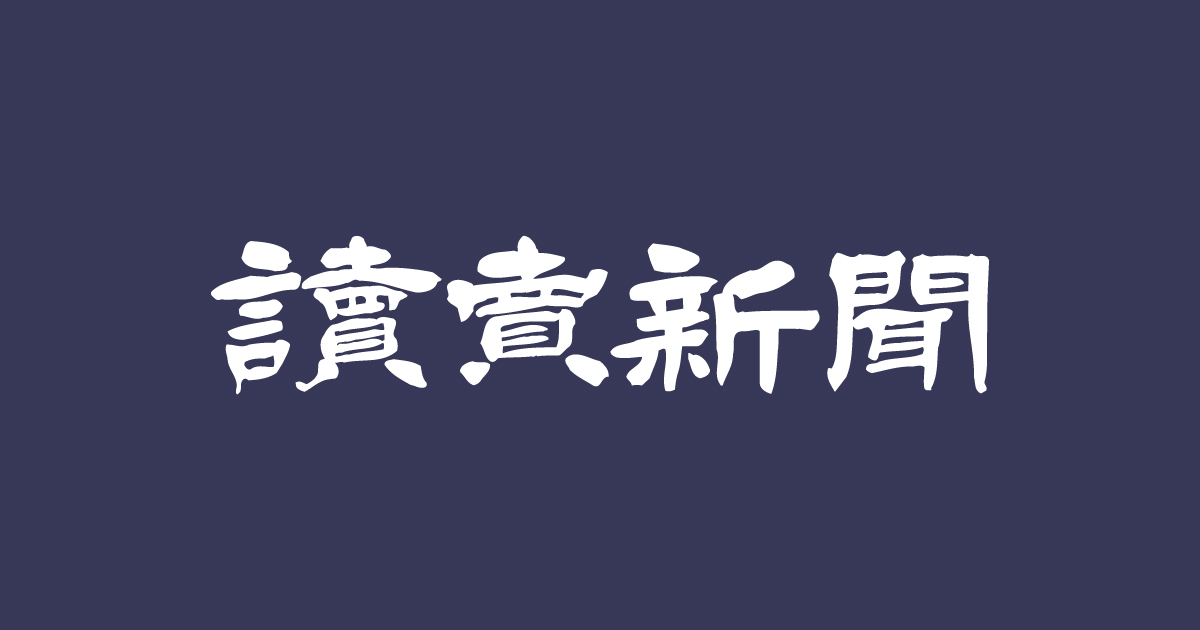





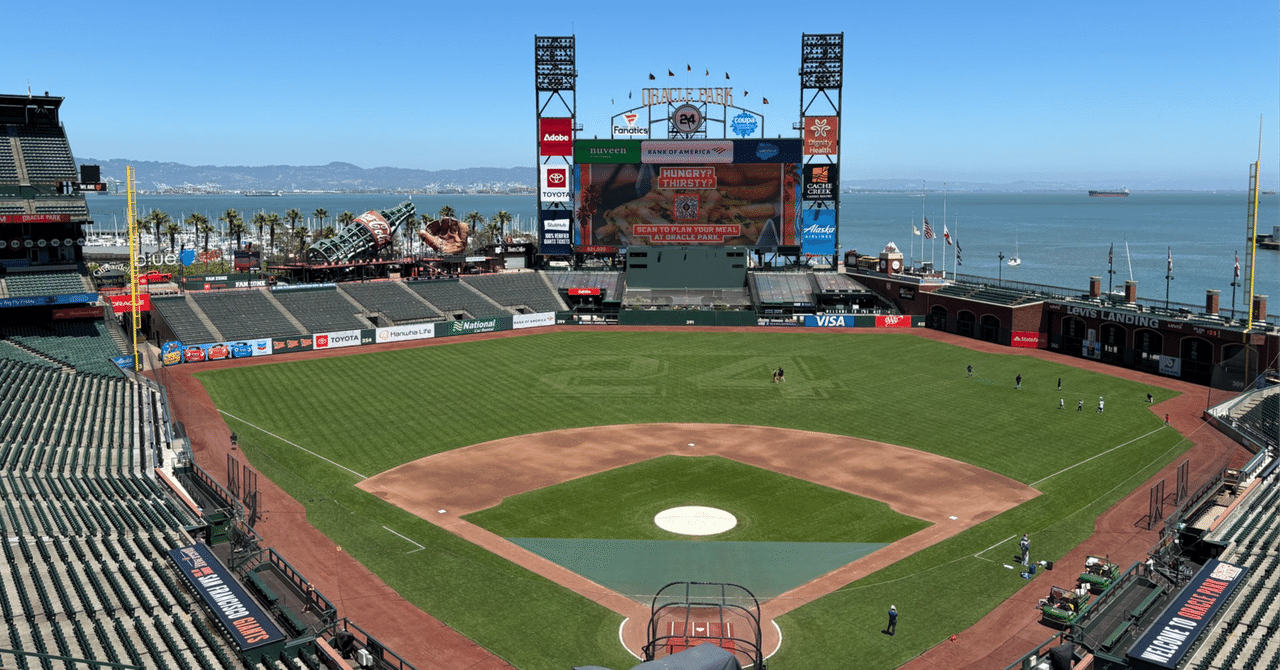


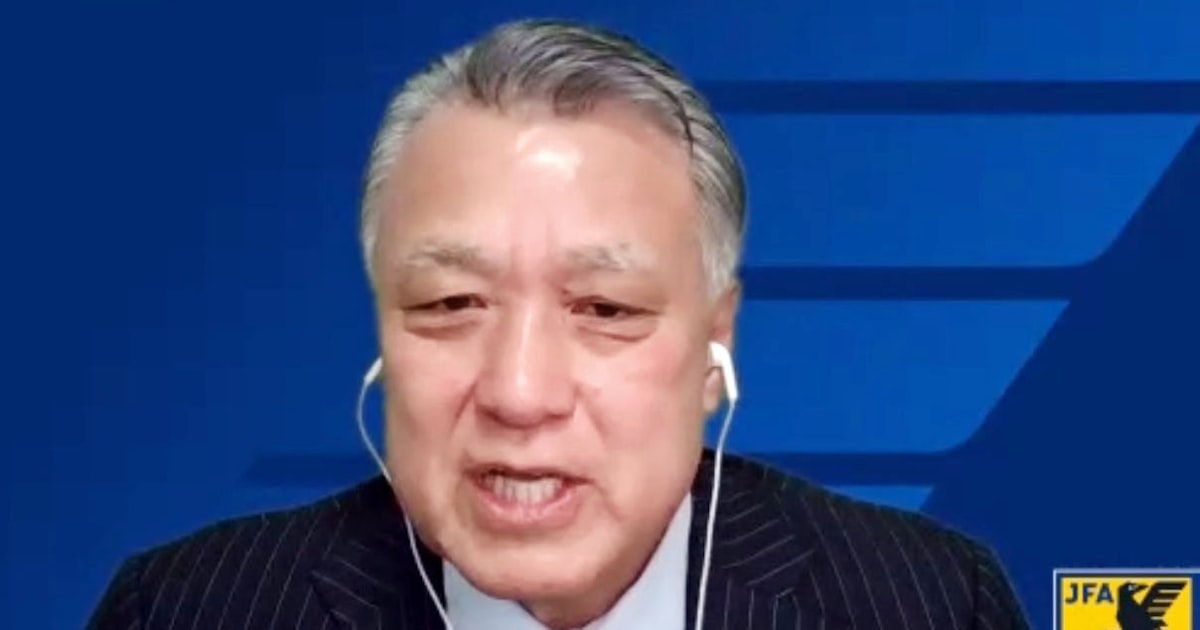



コメント